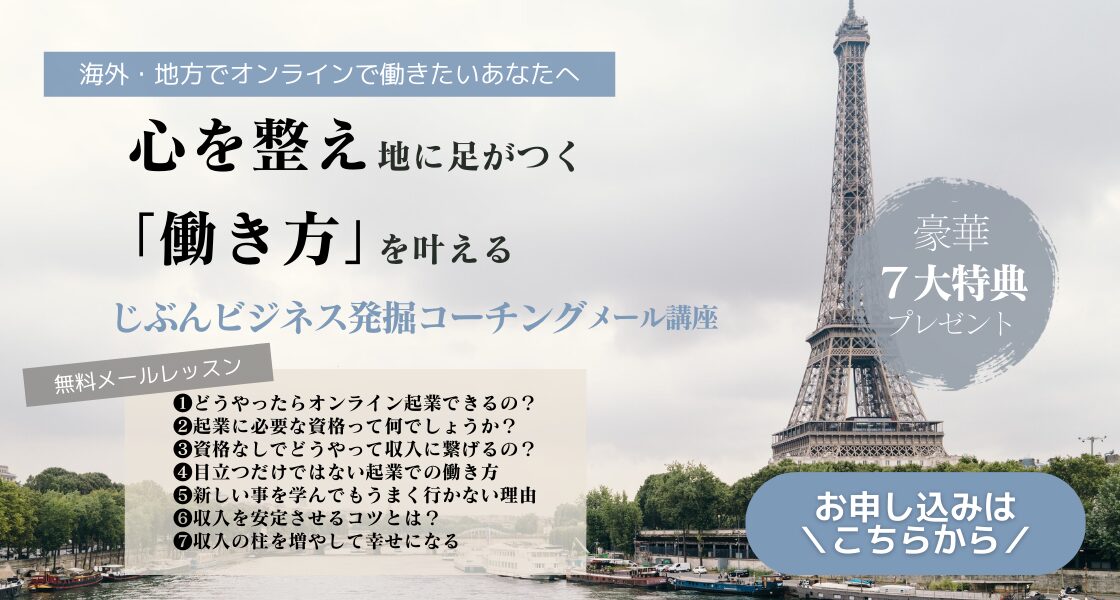フランスのワインには、いつも必ずラベルがついています。
「エチケット」とも呼ばれるワインのラベル、これは、ワインのさまざまな情報が詰まったワイン選びの情報源です。
このラベルの読み方がわかったら、ワインのことがもっと詳しくなれますね!!
ワインラベルの読み方について、まとめてみました。
[ad#rectangle]
ラベルに表示される主要項目
・産地(畑)名
・格付け
・造り手名
・商品名(ブランド名)
・ヴィンテージ
・ぶどう品種名
・アルコール度数
・容量
上記全てが記載されている訳ではありませんが、記載すべてがフランス語なのでフランス語がわからない人にとっては、最初から全てを把握するのは難しいです。
関連記事→ワインの開け方は?コルク抜きがない場合はどうする?失敗した時の対処法も
フランス語がわからない人にお勧めな簡単なラベルの読み方
フランス語がわからなくても、タイプ別に表示が微妙に異なることを理解しておくと、ラベルの読み方がずっとわかりやすくなります。
そのタイプについてまとめてみます。
関連記事→シャンパンのモエ・エ・シャンドンてどんなもの?価格はどれくらい?
産地(畑)名
これらは、主にフランス・ブルゴーニュ地方のワインに見受けることができます。
例えば「VosneRomanee」=ヴォーヌ・ロマネ、こればブルゴーニュ地方、ヴォーヌ・ロマネ村の名前がワイン名になっています。
その他にも「Bourgogne」=ブルゴーニュ、といった地方名がワイン名になっている場合などがあります。
関連記事→フランスのブルゴーニュワインの当たり年はいつ?味やボトルの特徴は?
格付け
格付けされている畑のワインでしたら「格付けの畑名だけ」や「その格付けされた畑がある村+畑名」が記載されます。
格付けとしては最高峰の「GrandCru」=グランクリュ(特級畑)、「PremierCruや1erCru」=プルミエクリュ(一級畑)があります。
例えば「RomaneeConti」=ロマネ・コンティ、これはヴォーヌ・ロマネ村の特級畑のワイン、例えば「VosneRomaneePremierCruClosdesReas」=ヴォーヌ・ロマネ・プルミエクリュ・クロ・デ・レア、これは一級畑のワインです。
また、上記の畑などは同じ畑でも複数の所有者が存在する場合がほとんどです。
つまり一つの畑を複数で分け合っているということですので「畑名+造り手」で見分けるとさらに細かく見極めることができます。
逆に一つの畑を単独で所有している場合、そのワインには畑名が記載されているだけでなく「Monopole」=モノポールと記載されています。
[ad#rectangle]
造り手名
主にフランス・ボルドー地方のワインに見受けることができます。
例えば「ChateauCalonSegur」=シャトー・カロン・セギュール、この「Chateau~」が造り手のワインということになります。
関連記事→フランスのボルドーワインの格付けをが知りたい!当たり年やシャトーも紹介!
商品名(ブランド名)
例えば「LaGrandeDame」=ラ・グランダム、これは造り手であるヴーヴ・クリコ社が手掛けるワインの中で最高級の位置づけにされている商品(ブランド)がワイン名になっています。
自動車メーカーのトヨタならば、レクサスといったところです。
関連記事→貴腐ワインって何?美味しい飲み方やオススメが知りたい!
ぶどう品種名
例えば「CabernetSauvignon」=カベルネ・ソーヴィニヨン、「SauvignonBlanc」=ソーヴィニヨン・ブランなどのぶどう品種がそのままワイン名になっているものもあります。
この場合、同じぶどう品種をいろんなワイナリーが手掛けていますので、「造り手+ぶどう品種」で見分けるとさらに細かく見極めることができます。
簡単に言えばこんな感じになります。
関連記事→ボジョレヌーボーの2016年の解禁日はいつ?出来はどう?
ワインのラベルの剥がし方
最近はスマホアプリなどで保管している人が多くなり、ラベルをはがす人は少なくなってきていますが、それでも飲んだワインが美味しかった場合にラベルを綺麗に剥がしてコレクションしたいという人はいるようです。
ラベルのはがし方ですが、ラベルコレクターと言う、ラベルをはがし、そのままファイリングできる専用のシールがあるのですが、それを使用しない場合は以下のものを参考にしてください。
1、空になった瓶に冷水を満タンになるまで入れます。
2、その瓶を熱湯が入ったバケツなどに入れます。
3、そのまま10分~15分ほど置いておきます。
※その間に瓶の水が熱くなったら冷水と交換します。
※ラベルを貼り付けているのりの強さで入れておく時間は異なります。
※決して瓶の中に熱湯を入れないこと、割れる危険があります。
4、上手くいけば、冷水と熱湯の温度差で自然とはがれます。
※ただし、スパークリングワインなどは氷水に入れる前提で強いのりで貼ってありますので、必ずしもこの方法で上手くいくは保証はできません。
[vin]
[rectangle]