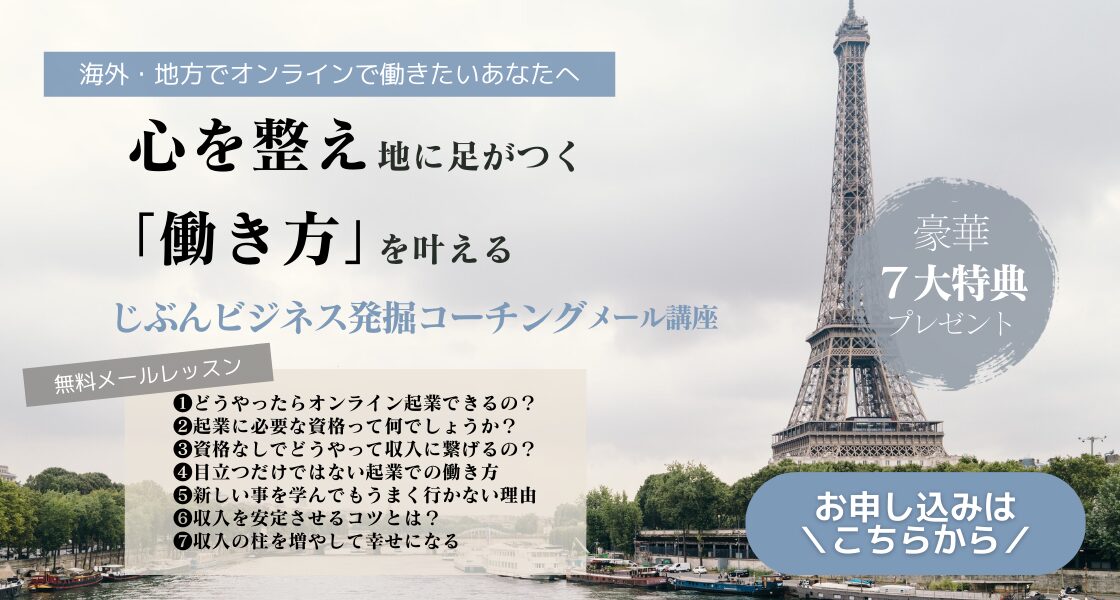フランスのワインと言って一番有名なのはやはりボルドーでしょうか。
ボルドーワインについて色々と知りたいですよね。
当たり年や特徴などまとめてみました。
[ad#rectangle]
ボルドーワインの当たり年(特にいい年)
※こちらに記載した以外の年が全部ダメと言っているわけではないですのでご注意ください。
2010
2009
2005
2000
1998(これは右岸のポムロール、サンテ・ミリオン地区)
1990
関連記事→フランスのブルゴーニュワインの当たり年はいつ?味やボトルの特徴は?
格付け
格付けは作られた地区によって異なっています。
メドック地区
1855年のパリ万国博覧会を機に時の皇帝ナポレオン3世の主導により制定。61シャトーによって構成され、筆頭の一級(プルミエ・グランクリュ)シャトー5つを称して五大シャトーと呼ばれます。
五大シャトーはシャトー・ラトゥール、シャトー・ラフィット・ロスチャイルド、シャトー・マルゴー、シャトー・ムートン・ロスチャイルド、シャトー・オー・ブリオンです。
ソーテルヌ、バルサック地区
こちらも1855年に制定されました。格付けワイン全て貴腐ワインで27シャトーによる構成です。
筆頭の一級(プルミエクリュ・シュペリエール)は「シャトー・ディケム」一つだけになります。
グラーヴ地区
1953年に制定後、1959年に改定されました。
16シャトーで構成されているのですが、上記の地区と違い「格付けされているか、されていないか」「赤だけ格付け、白だけ格付け、赤白両方格付けされている」と、ちょっと複雑です。
関連記事→フランスのボルドー観光に行こう!ワイン以外のお勧めは?
サン・テミリオン地区
1955年に制定されました。
基本、10年ごとに改定という規定なのですが、きっちり10年ごとではありません。
ちなみに1955、1958、1969、1984、1986、1996、2006年に改定されています。
82シャトーで構成されており、格付け筆頭(プルミエ・グランクリュ・クラッセA)は4つ(シャトー・アンジェリス、シャトー・シュヴァル・ブラン、シャトー・オーゾンヌ、シャトー・パヴィ)になっています。
ポムロール地区
あえて格付けは行っていません。
ボルドーワインはシャトーが複数の畑を所有して、その複数の畑からそれぞれ違うぶどうをブレンドして1本のワインを造る方法をとっているので、ワインを造っている「シャトー」に格付けをしたのです。
[ad#rectangle]
関連記事→ワインの開け方は?コルク抜きがない場合はどうする?失敗した時の対処法も
造り方の特徴
ボルドーでは、赤ワイン、白ワインそれぞれ複数のぶどう品種をブレンド(=アッサンブラージュ)して造られます。
赤ワイン用ぶどう品種は、メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド、マルベック。
白ワイン用ぶどう品種は、ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、ミュスカデル。
また、ボルドーでの赤ワイン用としてのぶどう品種の栽培面積が9割、白ブドウは僅か1割です。
関連記事→飲みかけのワインの保存方法は?未開封とは違う?保存期間はどれくらい?
貴腐ワイン
上記でも記載しています「ソーテルヌ、バルサック地区」ここにおいて昼・夜の温度差や近くに流れる川の影響による霧など複数の要因でぶどうに貴腐菌が付着します。
この地区で栽培されているセミヨンという品種に菌が付着することで、糖度の高いぶどうになり、極上の天然甘口ワインができます。
その貴腐ワインの中でも「ボルドー・ソーテルヌ地区のシャトー・ディケム」「ハンガリー・トカイ地区のエッセンシア」「ドイツ・モーゼル地区のトロッケン・ベーレンアウスレーゼ」これらを称して世界三大貴腐ワインと呼びます。
関連記事→貴腐ワインって何?美味しい飲み方やオススメが知りたい!
ボトル
一般的にボルドーワインのボトル形状のことを「いかり肩」と言います。
どうしてこのような形状なのかというと、ワインを長期熟成させる中で澱という色素が結晶化する現象が起きます。
長期熟成されたワインをグラスやデキャンタへ注ぐ際に、その澱が入らないように肩の部分で引っかかるようにこのような形状になっています。
またボトルの底がくぼんでいますが、そのくぼみに澱が溜まりやすくするためにこのようなくぼみがあります。
やっぱり理由があるのですね。
関連記事→フランスワインのラベルの剥がし方は?読み方も紹介!
関連記事→安くて美味しいワインの選び方が知りたい!
[vin]
[rectangle]