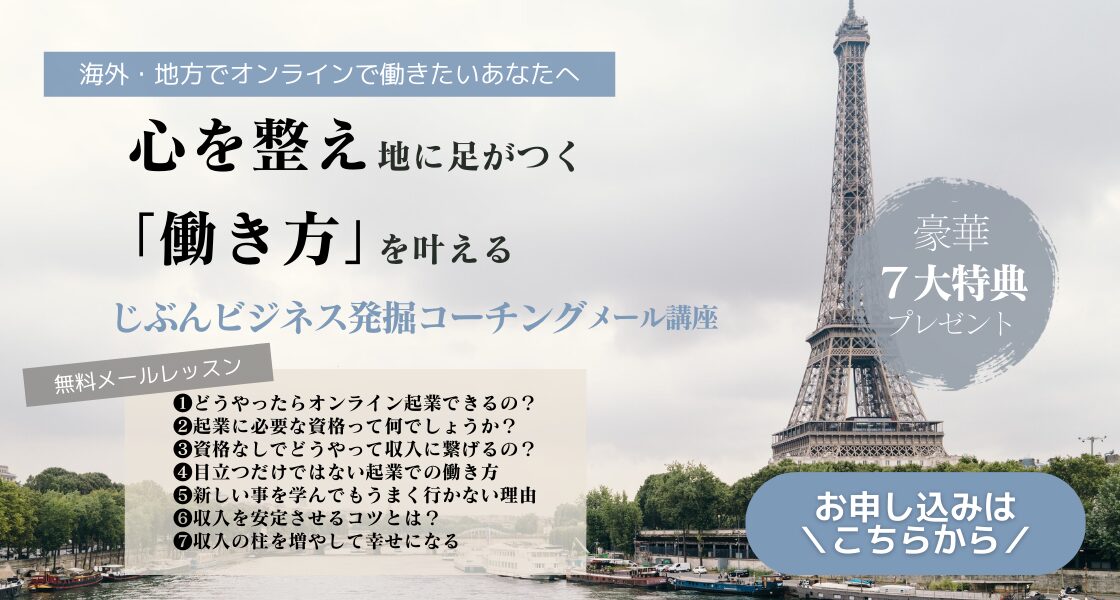ワインは種類が沢山あって、テイスティングをどうすればいいのか悩むという方は多いはず。テイスティングするときのポイントはどういうものでしょうか?方法や、表現方法について説明しますね。
[ad#rectangle]
関連記事→ワインの産地や特徴を説明!フランス・イタリア・スペインなど
ワインのテイスティング方法
ワインは、使用するグラスによって味わいが大きく変わります。赤ワインを大きなグラスで飲むイメージがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ブラインドテイスティングといって、中身を知らされないまっさらなイメージの状態でテイスティングする場合は、AOCグラスと呼ばれる小ぶりなグラスを使ってすべてのワインの味や香りを平等な状態で評価するのが一般的ですが、一般的なテイスティングの場合、グラスは赤ワインでも香りや味わいの強いボルドーブレンドのものは深くて大きなグラス、主にピノ・ノワールのような繊細なワインは口よりロコ底の方が横に広く太ったグラスを使います。
白ワインの場合は、ボルドーグラスより小ぶりなもので飲むことが多いですが、明るくて軽やかな味わいの赤ワインも同じグラスで飲むことがあります。
ワインは、空気を含ませると酸化して香りがたち、味わいも変わります。ワインを飲む前にグラスを回すのは、ワインに空気を含ませているのです。
回すときは、右利きの人は右回し、左利きだと左回しに回します。これは、万が一回しすぎてワインが飛び出してしまったときに、人がいる方向ではなく自分の側にワインがこぼれるようにするためです。
[ad#rectangle]
関連記事→ワイン用のブドウ品種の特徴を一覧に!おすすめはこれだ!
ワインの香りの表現は?
ワインの香りは、さまざまなもので表現されます。ベリーやトロピカルフルーツなどの果物はもちろん、黒鉛や石油などのとてもおいしそうには聞こえない表現が使われるのも、ワインの表現の特徴です。
黒鉛香や石油香は、決して劣化していたり出来が悪かったりするワインに使われる表現ではありません。ワインの香りはたいへん複雑なので、単純にかぎ分けることのできる香りは、素直に似た香りのものに例えられるのです。
といっても、初心者が黒鉛香や石油香を感じ取るのは難しいですよね。まずはベリー系の香りや、トースト香など、比較的わかりやすい香りを感じ取れるようになりましょう。
ワインの香りの勉強用に、ワインの香り標本も発売されています。一般的に使われる表現のものはもちろん、劣化したワインを見分けるための標本も入っているため、トレーニングすることができます。
ワインの味の表現は?
ワインの味も香りと同じで、素直に感じた近い味のものに例えて表現されることが多いです。したがって必然的に比喩が多くなります。また、「正しい表現」は存在しないので、自分の思ったことを表現することが大切です。
参考書などを読むと、「爽やかな草原のような」「ミントなどのハーブのような」など、自分では思いつかないような言葉が並んでいると思います。これは、必ずしもこういった洒落た表現をしなければいけないわけではありません。
例えば「チョコレートのようだ」とか「ハチミツのようだ」「ラズベリーやクランベリーなどのベリーの味わい」「煮詰めたジャムのような果実感のある味わい」など、感じたことを表現すればよいです。
自分で忘れないために記録する分には感じたままに書けばよいですが、人に伝えるにはどうしてもわかりやすい言葉にする必要があります。少しずつ、伝わりやすい表現ができるように意識していくと良いです。
ワインのテイスティングノートの書き方
ワインは世界中に数えきれない種類があり、自分の飲んだワインの味をすべて覚えて置ける人はいません。でも、せっかく飲んだワインの味を忘れてしまうのはもったいないですよね。そんなときは、テイスティングノートをつけると良いでしょう。
テイスティングノートというとハードルが高く感じるかもしれませんが、要は感じたことをメモすれば良いのです。
基本情報としては飲んだワインの名前、作り手の名前、だいたいの値段、ブドウ品種、セパージュ、ヴィンテージ、生産地などを書いておきます。そして必ず、つたない言葉で良いので自分で感じた香りの特徴と味の特徴、もし時間をかけて飲んで、飲んでいる間に香りや味わいが変わった場合にはその変化についてなど、気が付いたことを何でも書いておくと良いです。
また、感動した食べ合わせや合わなかった食べ合わせなども記録しておくと後で必ず役に立ちます。
関連記事→ワイン初心者にもおすすめ!種類や選び方のまとめ記事
[vin]
[rectangle]