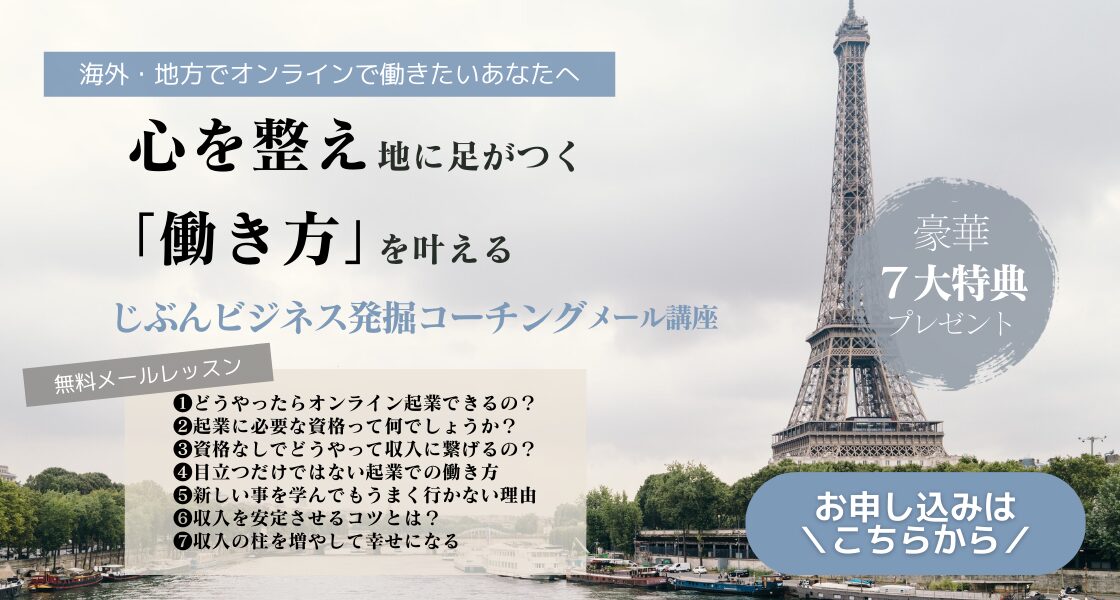ワインは色んな品種のブドウを使って作られます。それぞれの品種によって、特徴が違い、また配合やどこで作られるかによっても、ワインの味が変わってきます。
ツヴァイゲルトの品種の特徴やおすすめのワイン、一緒に食べると美味しい料理などについて説明します。
[ad#rectangle]
関連記事→ワインの産地や特徴を説明!フランス・イタリア・スペインなど
ツヴァイゲルトのワインの特徴
ツヴァイゲルトから造られるワインはやや紫がかった赤色をして、タンニンが強いワインとなります。香りはベリーや控えめなスパイスも感じさせる、フルーティーさの強い香りがします。
十分に熟成させるとサワーチェリーのような風味を持つワインとなります。早飲み用の若いワインもあれば、オーク樽で熟成させる高級ワインまで幅広いスタイルを生み出します。ツヴァイゲルトはタンニンの強いワインを造り、十分に熟されるとサワーチェリーを持つ風味を持つワインとなります。
ツヴァイゲルトの品種
ツヴァイゲルトはオーストリア原産の赤ワイン用品種です。1922年にツヴァイゲルト博士に開発された品種で、耐寒性に優れている比較的新しい品種でありながら、オーストリアにおいて最もメジャーな品種になっています。比較的寒冷な地でも栽培が可能な品種で、オーストリアで最も広く栽培されていて、日本においても東北以北で栽培されています。
葉は丸形から五角形となっており、ブトウの房は中くらいで、円筒形をした円い青黒い色の実をしています。ツヴァイゲルトから造られるワインは若飲みタイプから長期熟成タイプまで様々なワインが造られます。
ツヴァイゲルトの主な産地
土壌に対しては特別な条件はありませんが、樹勢が非常に強い特性を持っているので重点的なリーフワークと収量制限が必要となります。カリウムが不足してしまうと収量が少なくなってしまうといった悪影響を及ぼしてしまい、水分過不足や養分不足、ストレス、葉と果実のバランスが悪い、極端な気温の変化などによって成熟期にブドウが萎えてしまうことがあります。
熟するのは問題なく出来ても、収穫期に発生しやすい灰色カビ病に対して弱い特性があります。粒同士が密着し過ぎていると風通しが悪くなるのでそこから病気が発生しますので、1年の作業の殆どを収穫期の灰色カビ病の対策に時間を使います。
収穫時期は9月中旬から10月上旬です。他の黒ブドウよりも少し早い時期に収穫が始まる傾向があります。
[ad#rectangle]
関連記事→ワイン用のブドウ品種の特徴を一覧に!おすすめはこれだ!
ツヴァイゲルトの味や香り
プラムにカシスやブラックベリーのような黒い果実を煮詰めた香りがし、シナモンやグローブのようなスパイスの香りも楽しめます。少しスミレや土の香りもします。口にすると柔らかさの中で果実の凝縮感とバランスの良い酸味、後味はキメが細かい渋みを感じ、黒い果実の印象が余韻として残るワインです。ジューシーだけど重たく感じません。
ツヴァイゲルトワインはブドウの熟成の仕方により風味が変わります。よく熟されたツヴァイゲルトから造りだされたものはクルミに似た香りとスパイスをミックスさせたような味わいがあります。若いツヴァイゲルトから造られたワインはサッパリとした味わいで香りが優しく、魚料理とも合いそうな軽いテイストのワインに仕上がります。
ツヴァイゲルトのワインのおすすめ
「北海道ツヴァイゲルト」です。しっかりとした色調で、スパイシーな香りを感じます。渋みが柔らかく、果実味を感じられる辛口のワインです。このワインは余市で生産されたものを使っています。余市の温暖な気候と土壌が高糖度のツヴァイゲルトに仕上げています。牛やラム、エゾ鹿などの肉料理やウナギやブリなどの魚料理とも相性が良いです。
2つ目のおススメワインは「ツヴァイゲルト・クラッシック ヴァイングート・グラッスル」です。オーストリア産のツヴァイゲルトを100%使用しています。深いルビー色にダークチェリーやブルーベリーなどを連想させるフレッシュな香りを感じ、口中で程よい渋みを感じられます。
ツヴァイゲルトに合う料理
ツヴァイゲルトに合う料理は肉料理、和食、中華料理、パスタとの相性が良いです。香りの中に烏龍茶の茶葉を思わせる香りも感じるので、中華料理やアジア系の料理ともよく合います。
食材としてキャベツの蒸し煮やハンバーガー、グリルソーセージ、ウナギの蒲焼、味わいがしっかりとしたチーズとも相性が良いです。ツヴァイゲルトが使われているワインは重ための味わいなので、肉などのガッツリ系の食材やメニューと合わせるのがおススメです。
関連記事→ワイン初心者にもおすすめ!種類や選び方のまとめ記事
[vin]
[rectangle]